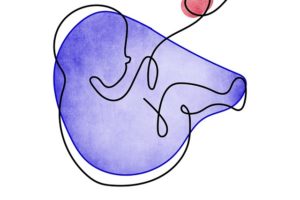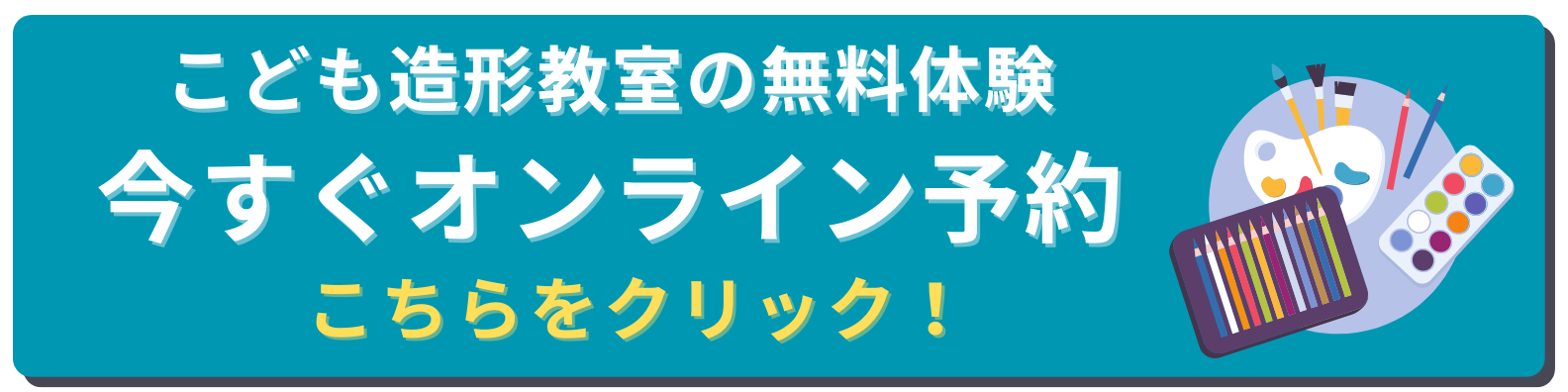「はやく起きなさい!」
「宿題しなさい!」
「歯は磨いたの?」
毎日ガミガミといわなくても、サッと動いてくれる子どもになってくれたら!
世のお父さん、お母さんは、子育てをしているとそう思うことがあると思います。
毎日思っているのは、Rinだけではないかもしれません。
どうしたら、子どもがサクサク動くようになるか、ちょっとしたコツを自分のために、勉強したので、忘れないように記事にしてみました。
時間管理ができる子に育つ3つのコツ
-
【できたこと】をみつける
ついつい子育てをしていると子どものできないところやマイナスな部分に目がいってしまいがちですね。
そこで、【できたこと】をみつけ、認めてあげる習慣をつけていくようにします。
たとえば、靴が並んでいなくても、ランドセルを定位置の棚などにおけたら、
「ランドセルのたなに置けたね!」
とできたことに対して、声をかけていきます。
ついつい、
「靴が並んでないじゃない!」
といってしまいそうになっても、グッとこらえます笑。
「自分で動く」
という原動力は、
【自分でできた→自己肯定感】から育まれます。
親が声をかけてあげることで、自己肯定感を高めてあげることが第一優先させていくことです。

-
【共感】+【問いかけ】のセットで!
「ただいま!」と学校帰ってきた子どもに、ついつい
「すぐ宿題終わらせなさい。」
「塾の時間、もうすぐよ。」
「洗い物はない?」
などなど、いいたいことは山ほどあるけれど、
まずは、
「6時間あって大変だったね。」
「外は、寒かったでしょう。」
などと、子どもの気持ちを共有します。
「お父さん・お母さん、わかってくれてるな。」
という安心感が一日がんばった子どもの心をほぐしていきます。
そこで、
「じゃあ、なにから始めようか。」
と問いかけます。
そのように問われたら、子どもも
「急いでおやつ食べてから、塾の準備をしようかな?」
と自分で考えて決めることができます。
-
【ついで】にできることをやってしまう
人間の脳は、新しいことを嫌がるそうです。
だけど、毎日行っている行動や習慣に【ついで】にできるようにするとすんなりとできるようになるそうです。
たとえば、帰ってきたら、靴をそろえる。ランドセルを置いたら、その流れでプリントを出すなど、やるべきことを今までの行動や習慣に組み込んで【ついで】にできるようにしていきます。
最初は、こどもの動線にあわせて、身につきやすいように収納や提出場所など工夫しながら、「お帰り!靴、そろえようね!」など、明るく声かけを続けると、自然に定着しやすいです。
まとめ
「どうして、なんでも言わないと動かないの?」と悩んでいるお父さん、お母さんは、がんばりすぎているのかもしれません。
きっとどんなお父さん、お母さんも、
【親の思い通りに動くようにさせたい】
のではなく
【自分で考えて行動できる。】
ようにさせたいのではないでしょうか?
このように
【自分で考えて行動する。】
ことは、これからの時代、より求められる力です。
単純作業は、減っていき、いろいろなことを同時に処理したり、複雑なことを考えていくようなことも大切になってきます。
このようにこれからを生き抜いていくためにも、子どもの頃から
【自分で考えて行動する。】
そして、
【時間を管理する】
ことを練習していくことが大事だと思います。
Rinも、3つのコツを心に刻んで、日々子育てに励みたいと思います!