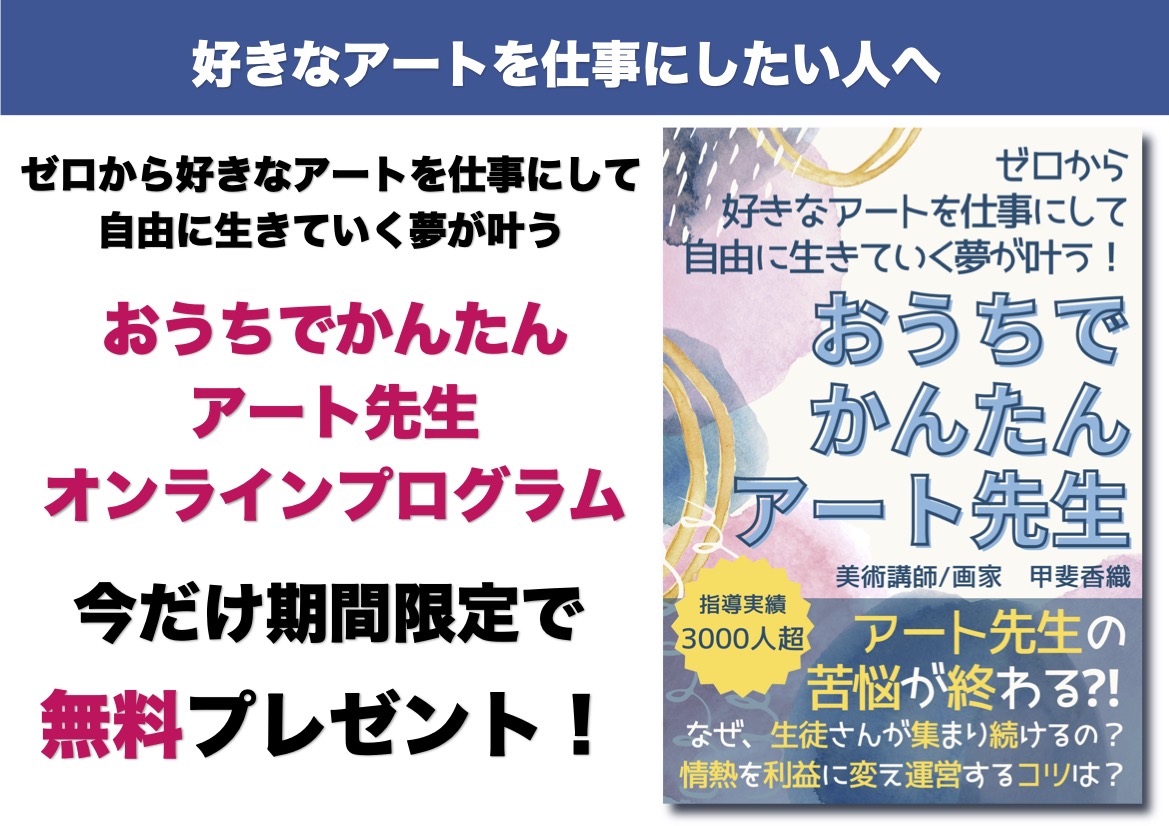こんにちは!母画家道Rinです。
墨を使って平面に表現する方法として、水墨画がありますね!
今日は、学校や家庭で取り組む時の水墨画のいろいろな道具についてご紹介していきます。
墨とは?


墨は何からどうやってつくられているのか意外に知らないですよね。
墨は、油煙やマツ材を不完全燃焼させてできた煤(スス)を膠(にかわ)で練り固めだものだそうです。
水で一緒に硯(すずり)ですって液体状にして使用しますね。
けれど、普段、私たちが使うのは最初から液状になった状態で売られている墨汁、墨液が多いです。
硯ですったりする手間が省け、すぐに使えるので手軽で便利ですね。
墨汁には、天然の煤(スス)を使ったものだけでなく、化学的につくられたカーボンを使っているものもあります。
薄めて使うものと、そのまま使うものが墨汁、墨液にはあるので、使う前に確認してから取り組みましょう!
↓これは薄めて使うタイプです。
水墨画を描くときの紙は?
西洋紙や画用紙などにも描くことができるけれど、墨ならではの濃淡やかすれやぼかし、にじみなどといった表現を楽しむのなら、和紙や半紙などを使うと効果的ですね。
和紙にもにじみやすいものとそうでないものがあるので、使う前に試しがきするといいですね。
水墨画を描くときに使う道具は?


できれば、絵の具用の筆ではなく、墨用の筆を用意することをお勧めします。どうしても墨が筆に残り、絵の具を使うときに濁りの原因になったりするので。
筆の他にも、いろいろな幅の刷毛(はけ)やスポンジ、綿(わた)、タワシ、縄、段ボールなども使うと表現の幅が広がりますね。
あると便利なもの


溶き皿
墨汁や水を入れておくために、溶き皿があると便利ですね。無ければ、紙皿やプラスチック皿などでも代用できます。
文鎮やフェルトの下敷き
文鎮は和紙や半紙を押さえるのに役立ちます。下敷きは和紙などの下に引いて使います。フェルト製のものが多いです。なければ、新聞をひきます。
習字道具セットに入っているので、子どもたちとするときはあそこから使うといいですね。
水墨画の表現


かすれ
少しの墨を筆につけて勢いよく動かすとかすれさせることができます。
にじみ
和紙や半紙などに刷毛などで水を塗り、墨をつけるとお花が咲くようにゆっくりと広がります。
他にも先に墨を塗り、その周りを囲むようにして水をつけると形がぼかされる効果があります。
水の量や付け方によって効果が変わってくるので、いろいろな方法を自分なりに試すと面白いですね。
水墨画用の和紙を使うと効果がわかりやすいです。
濃淡
墨は水の量を変えて行って、濃淡を表現することができます。
水の量が少ないと濃くなり (濃墨)、半々くらい(中墨)、水多めだと薄く(淡墨)なります。
まとめ
墨は五彩を表すというように、白黒の濃淡だけでなく、そこに色味を感じさせる魅力もあります。黒の濃淡だからこそ、逆に彩りのイメージが広がりやすいです。
それに、水墨画というと難しく、硬く、伝統的なイメージもあってちょっと、気後れしたり身近に感じにくかったりするかもしれません。
そんな時は、墨象画といった文字からイメージを広げたりする方法もあったり、抽象的な表現から入るのも一つですね。Rinも授業でよくといいれる方法です。
もっと、詳しく水墨画の技法も、今後、ご紹介していきたいと思います!
最後まで読んでくださりありがとうございました。
また、違う記事でもお会いできると嬉しいです!