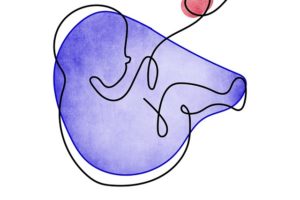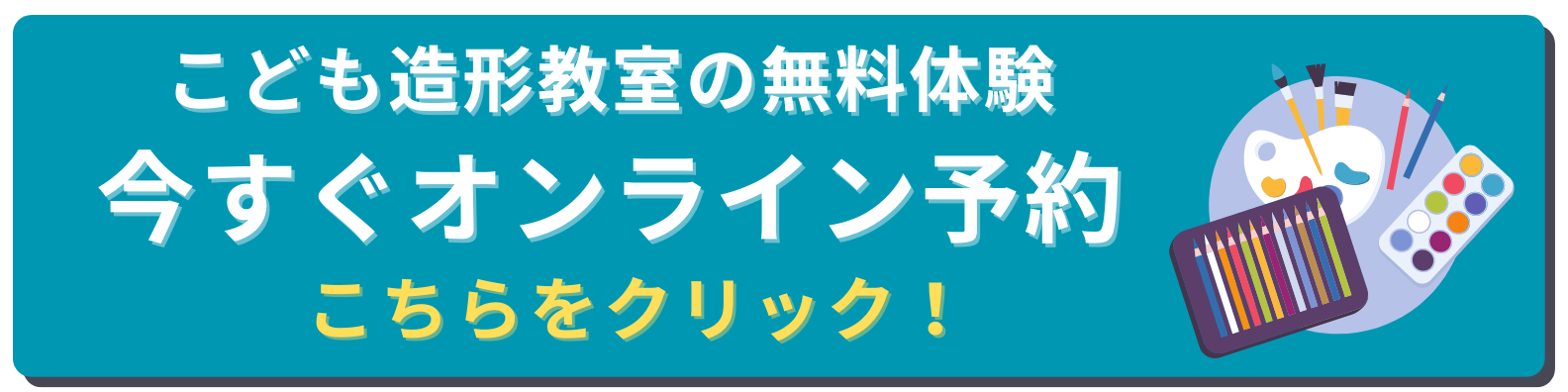こんにちは!母画家道 Rinです。
前回は、クレパスとクレヨンの違いについてお伝えしました。
今日は、クレパスやクレヨンの使い方や片付け方の方法やコツをお伝えしていこうと思います。
クレヨンは幼稚園児や保育園児などの未就学児さんに小学校低学年に使いやすいもので、クレパスはその特徴から幼稚園児や保育園児などの未就学児さんはもちろん、小学生や中学生、高校生、大人や専門家まで使いやすい表現の幅があります。
そんな身近で誰もが、一度は使ったことがある手軽な描画材
クレパスとクレヨンの使い方や片付けの方法やコツなどをお伝えしていこうと思います。
目次
・えんぴつを持つように持つ
・上からつまんで持つ
・にぎって持つ
・制作中の置き方
・色が混ざってしまうときは
・折れたり小さくなったりしたときは
・長いのにラベルの紙がとれたら
・片付け
⑴ 持ち方

クレヨンやクレパスはいろいろな持ち方ができます。
持ち方によっていろいろな表現ができます。
・えんぴつを持つように持つ
一般的には、鉛筆を持つときのように持って、描く場合が多いと思います。
握る場所が上過ぎると力を入れたときに折れるので、下の方を持ってていねいにかくようにするのがコツです。
・上からつまんで持つ
クレパスやクレヨンを上からつまむように持って描くこともできます。
小さくなって鉛筆を持つように持ちにくくなったときや横にして広い面をえがきたいときにも、オススメの持ち方です。
鉛筆持ちに比べると力が入りにくいけれど、その分、やわらかい表現ができます。
・にぎって持つ
棒をにぎるようにして持ちます。幼稚園児や保育園児などの未就学児さんで
はじめてクレヨンやクレパスを使ったときにも多い持ち方です。
手の力がそのまま、クレヨンやクレパスに伝わるので、弱い力でも線が描けるし、濃い線を描くこともできます。
点々を描きたい(点描)ときも、この持ち方をすると紙に打ち付けるようになるので描きやすいです。
⑵ 取り扱い方

・制作中の置き方
制作中、使っているクレヨン・パスは、その都度元に戻すか、フタか新聞紙・ティッシュ等の上に置いておく習慣をつけるといいです。
ついつい夢中になって、バラバラと画用紙の上にバラバラに置いたり、何本もてにもったりしたい気持ちもとてもよくわかります。Rinもよくしています。
けれど、そうしていると画用紙を汚したり、クレパスやクレヨンの欲しい色を探すのに時間がかかったりして、かえって時間がかかったりスムーズにいかなかったりしてしまいます。
最初にきちんと習慣や良い癖をつけるのは大切ですね。
・色が混ざってしまうときは
クレヨン・クレパスは、他の色が先の方についたり混ざったりすることがよくあります。
そのまま使うと濁った色になってしまったりしますよね。
そんなときは、いらない布やティッシュペーパーなどでお汚れをふきとるようにするといいです。簡単にふきとれるので、クレヨンやクレパスを使うときは、用意しておくと便利なアイテムです。
・折れたり小さくなったりしたときは
クレパスやクレヨンは、鉛筆などに比べるととても折れやすいです。
だけど、折れてしまったからといって、すぐに捨ててしまうのはもったいないです。
そんな折れてしまったり、小さくなってきてしまったりしたときは、巻いてあるラベルを取ってしまって広い面をぬるときなど、面塗りようにするといいですね。
・長いのにラベルの紙がとれたら
クレパスやクレヨンには、扱いやすいように長い胴の部分に、紙のラベルがまかれています。理想は、少しずつはがしながら使うのがいいのですが、うっかり全部とれてしまうことがあります。
そのままでも使えるのですが、直接クレパスやクレヨンを手でふれるので、指が汚れその汚れた指で画用紙などをさわると画用紙が汚れてしまったりしますので、オススメしません。
なので、とれてしまったときは、コピー用紙など巻きやすいやわらかい紙をクレヨンやクレパスの長さに合わせて切って、胴の部分にまいてあげるといいですね。
紙をとめるときは、セロハンテープでも悪くないですが、あとから少しずつ剥がすことを考えるとノリのほうがオススメです。
・片付けの仕方
クレパスやクレヨンの先について他の色や汚れを布やティッシュなどで拭き取ってから、箱にしまいうと次に使うときに気持ちよく使えます。
小さくなったモノなどは、落としたりしやすいので、気をつけるようにします。
そうしないと、上靴でふんで気づかずに歩くと、床がクレヨンやクレパスまみれになってしまうからです。
クレヨンやクレパスは、紙製の箱に入っていることが多いので、ゴムなどで箱が開かないように工夫しておくといいです。そうしないと、縦向きに鞄に入れたときにバラバラと出てきてしまうからです。
ゴムなどを利用するときは、箱の裏にガムテープなどでゴムをとめておくと、ゴムがなくなったりせずに便利ですよ。
⑶ まとめ
今日は、クレパスやクレヨンの取り扱い方や片付け方の方法やコツをおつたえしました。
身近で扱いやすい描画材なので、気軽にいつも快適に使えるといいですね。
コンテとパステルの違いについてもご参考にされてください。
では、最後まで読んだくださりありがとうございました。
Rinでした。