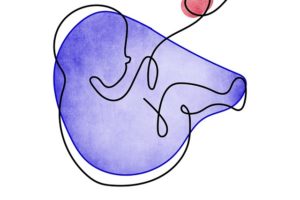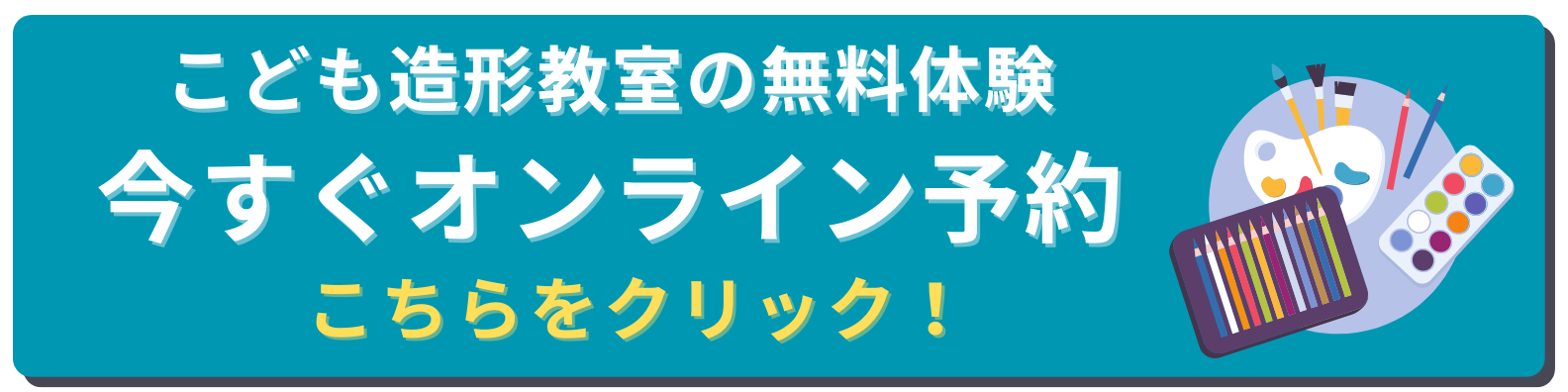こんにちは!母画家道Rinです。
今日は、粘土の種類【前編】です。
小学校の図画工作や中学・高校の美術まで大活躍!粘土の特徴や用途、使い方を種類ごとにご紹介していきます。
粘土(ねんど)といっても、実はいろいろなモノがあります。
その中で、大きく分けると7種類にわけられます。
-
紙粘土
-
軽量粘土
-
液体粘土
-
小麦粉粘土
-
液体粘土
-
土粘土
-
油粘土
粘土の種類【前編】
今日は、その中でも、
について粘土の種類【前編】としてご紹介していこうと思います。
-
紙粘土とは?
特長
紙粘土とは、パルプを材料にしてのりで混ぜてつくったものでした。
だけど、現在は扱いやすいように改良されてきました。
例えば、パルプに石粉などが混ぜられたものが売られています。
また、パルプ、石粉に木粉を混ぜた木のような質感をもつ木粉粘土(木くず入り粘土)なども商品化されていて、表現の幅を広げてくれています。
紙粘土は乾燥していくと固まります。
絵の具などで、色を塗ることもできます。
心材に使用できるモノも多いです。
用途
用途としては、小さなモノをつくったり、ビンや缶につけたりすることに向いています。
絵の具を練り込んで色粘土をつくって表すこともできます。
重さもあるので、土台などにつかうこともできます。
軽量粘土とは?
特長
軽量粘土は、樹脂中空体やパルプなどを主な成分としている粘土です。
とても軽いので、モビールに使ったりできます。
けれど、軽いので、土台などにはむいていません。
さまざまな芯材にくっつき、収縮率も低めでひび割れもほとんどありません。
用途
とても軽いので、重さを必要としなければ、紙粘土とほぼ同様の使い方ができます。
絵の具を練り込んだり、表面にぬったりもできます。
Rinの主宰する「こども造形教室」では、
おすし
をつくりました。
中学校の美術では、お弁当をつくったり、小学校の図工でも、よく使っています。
ホイップタイプもあります!
樹脂粘土とは?
特長
樹脂粘土は、樹脂を主な成分とした粘土です。
薄くのばすことができます。
着色をするときは、アクリル絵の具が適しています。
用途
細かいモノやうすいものをつくるときに、オススメの粘土です。
中学の授業で、和菓子をつくるときには、この樹脂粘土を使っています。
使っている樹脂粘土は、
「かた丸くん」です。
乾くとほんのり半透明になるので、和菓子の質感によく似ていて、まるで本物の和菓子のような仕上がりです。
小麦粉粘土
特長
小麦粉粘土は、小麦粉を材料としています。
なので、謝って口に入れても安全な粘土です。
値段は、紙粘土にくらべると少し高めです。
用途
口に謝って入れてしまっても、小麦アレルギーなどなければ、安全なので幼稚園児や保育園児などの幼児が扱う場合にオススメです。
液体粘土
特長
液体粘土は、紙粘土に水を加えて液状にした粘土です。
まるで、彫塑でつかう石膏のように固まります。
だけど、石膏のように水で溶いたりする必要もなく、石膏のように乾燥が早いわけではないく、ゆっくりなので、小学生でもあつかいやすいです。
絵の具を溶かし込んだり、乾いたあとに色をつけたりすることもできます。
用途
液体粘土に、古布やタオルなどを浸したり、ふりかけたりして固めることができます。
また、絵の具に混ぜて、描いたり、塗ったりすることもできます。
まとめ
今日は、粘土の種類【前編】をご紹介しました。
次回は、粘土の種類【後編】をお伝えしていきます。
お楽しみに!