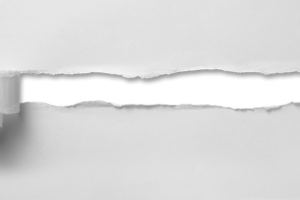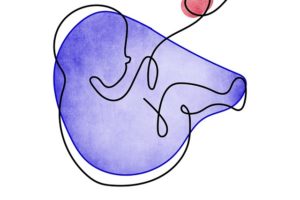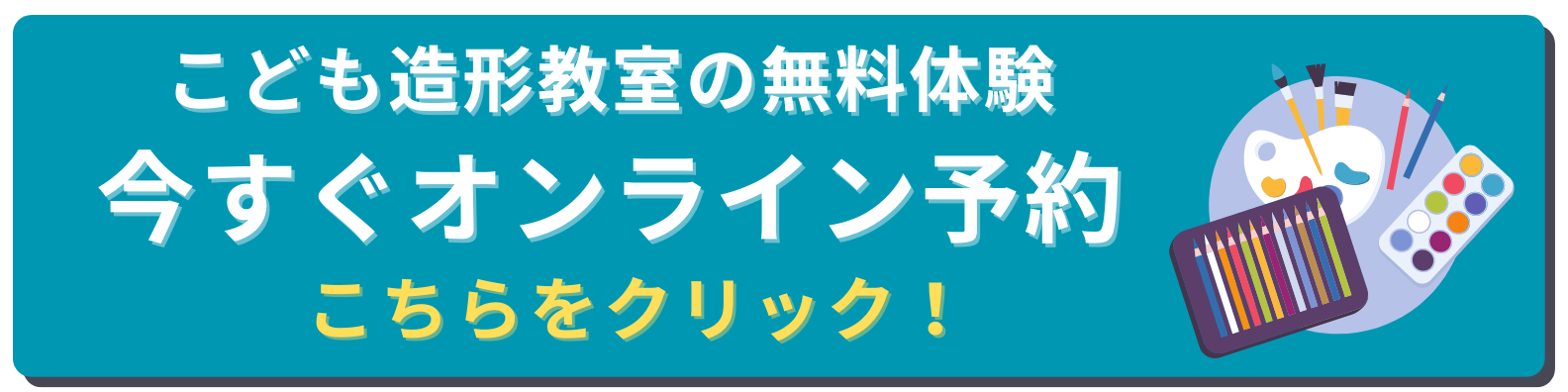こんにちh!母画家道Rinです。
子どもたちにとって、釘打ちは楽しい反面、日頃経験することもほとんどないので、難しい場合が多いです。
釘の長さは、一般的に打ち付ける板の厚さの2.5倍~3倍と言われているけれど、接合するものの厚さに合わせて、接着剤と併用しながら2倍程度の長さの釘を使うようにするといいです。
釘の太さは、釘の長さに比例し、太くなります。
釘を曲げない打ち方とは?
釘打ちをする場所は、堅く安定した台の上で行うようにします。
台が柔らかかったり、不安定だったりすると釘を打つときに弾んでしまったり、ずれたりしてうまく釘が入りません。
そんな場合は、堅く安定した台にかえるか、台がない場合は、堅い床などで打つようにしましょう!
釘を曲げないように打ち込むためには、
げんのうの頭を釘の打つ方向に合わせて頭の中心で打つようにします。
げんのうの頭を曲げたり、曲面の方で打ったりしないように気をつけます。
また、打つ瞬間に強く握りしめるようにすると上手に打てます。
キリで下穴を開けて釘をげんのうを持っていない方の指で支えながら打ちます。
釘が小さくて持ちにくいときは、ラジオペンチなどで挟んで持つこともできます。
板が割れたり釘が曲がったりしてしまうのはなぜ?

板が割れたり釘がまがったりする理由は、いろいろと考えられるけれど、その中でもよくある理由を3つお伝えしようと思います。
1つ目は
板の厚みに対して釘が太過ぎる場合
板の厚みが1㎝くらいなのに、5㎝も長さのある釘を打つと当然、釘の太さも太くなるので割れやすくなります。子どもの場合は、接着剤も併用して、板の厚さの2倍程度の長さの釘を使うようにします。(一般的には、接合する板の厚さの2.5倍~3倍の釘の長さを使います)
2つ目
木目部分が堅い木材の場合
木目(年輪)にそって釘が曲がって入ることで、釘が曲がってしまう場合があります。
そうならないためにも、キリで下穴をあけるのを忘れずに、釘打ちをしましょう!
3つ目
釘打ちの位置が板の端すぎる場合
これもよくあるパターンです。釘の太さもあるので、あまり端の方に打つと板が割れてしまいます。最低でも、釘の太さの2,3個分は端から離れた場所に打つようにします。
まとめ
今回は釘の打ち方について、お話してみました。
普段、釘を打つ経験をすることも少ないので、はじめて金づちを使う子もすくなくありません。なので、最初は接合することを目的にするのではなく、ビー玉迷路などつくったりして、釘を打つだけを目的にした経験を行うといいですね。
また、接合する場面でも、最初は曲がったりする経験もしながら、少しずつ慣れていくことも大切なので、失敗を恐れず、どんどん釘を打たせていくことが大切だと思います。
金づちの種類や使い方。図画工作でよくつかうのはげんのう!授業の悩みを解決しよう 。金づち・釘
釘抜きをするときの注意点やコツ、使う道具はこれ!安全に釘を抜くには?
も参考にされてください!