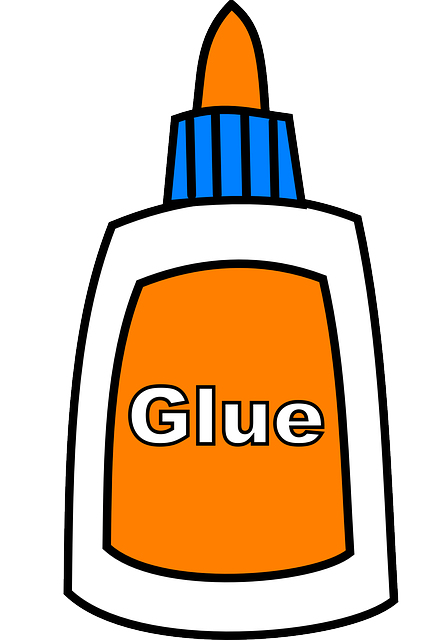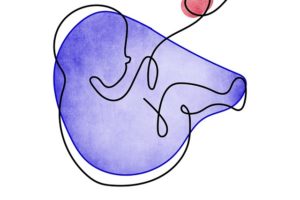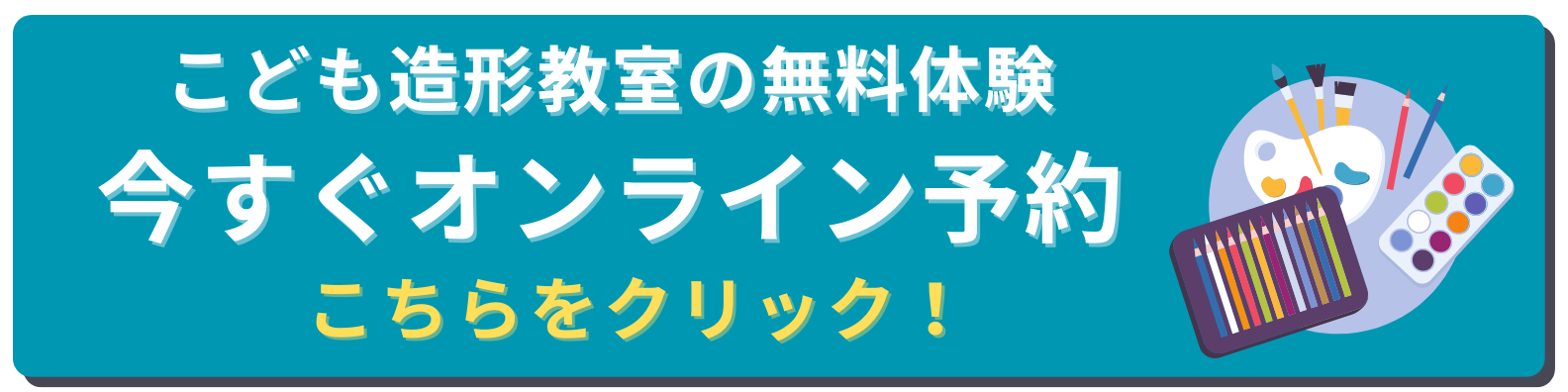接着剤の種類には、いろいろありますね。
今日は、そんなたくさんの種類の中から、図工や美術で使いやすいものをご紹介しようと思います。
授業でよく使う接着剤
学校で使う接着剤は、主に有機系と無機系に分けられます。
そして、有機系接着剤は天然系と合成系に分けられます。
よく授業で使っているのは、天然系のデンプンのりと合成系にの科学接着剤です。
デンプンのり

でんぷんに熱を加えてのり状にしたものです。
チューブやツボに入っています。紙同士の接着にも適しています。
昔は、保育園や幼稚園、小学校低学年によく使われていました。
けれど、最近では液状のりなど便利なので使う場合も多いですね。
だけど、特に未就学児などでは、指の感覚や器用さを高めるため、でんぷんのりを使わせている場合も多いです。
また、広い範囲に塗りたいときは、のりに水を少し混ぜてから、刷毛(はけ)などで塗るといいです。
障子を張り替える時に使うやり方ですね。
Rinが小さい頃、母が白ご飯を潰して、手作りで作ったのりで、障子の張替えをしていたのを思い出しました。
Rinは、古い障子を剥がすのを手伝っていました。
普段、破いたら怒られるけれど、この時だけは、思いっきりできるので楽しかったです笑。
使い方
新聞紙や広告紙などいらない紙をひきます。
のりを使う指を決めて、貼りたい部分に均一に薄く伸ばすようにしてつけます。
オススメの指は、中指です。指にのりがついたままでも、紙が持ちやすいからです。
けれど、濡れタオルなど用意しておくとすぐふけるので、一番塗りやすい人差し指でも、大丈夫ですね。
ステイックのり

主な成分はポリビニルピロリドン(PVP)樹脂です。
容器の外側の下を回すとスティック状の固形のりが出てきます。
手を汚さずに均一にぬれるし、液が漏れたりもしないので便利です。
液状のり

主な成分は、ポリビニルアルコール(PVAL)です。
紙やセロハン、布などの接着ができます。
補充もできるので、図工や美術の授業でもよく使われています。
出るところの網目が痛んだり、固まったりすることもあるので、交換するといいです。
しっかり締めておかないと、倒れたときなどノリが漏れるので注意が必要です。
木工用接着剤

木工用とあるように、木をつけるのに適しています。
木の他にも、かみや布、プラスチックなど幅広く使われています。
色は、白色をしているけれど、乾くと乳白色に近い透明になります。
酢酸ビニル樹脂エマルジョン系の接着剤です。
接着以外にも、土と混ぜて土絵の具を作ったり、絵の具と混ぜて、マチエールを(絵の具を盛り上げて凸凹を出す)作ったり、
プラスチック板などに薄く延ばして、ステンドグラス風にしたりといろいろな使いかたができます。
まとめ
今回は、学校で使う接着剤の代表的なものをご紹介しました。
接着剤は、接着したいもの同士に合わせて選ぶことも大切です。
次回は、化学接着剤についても、ご紹介していこうと思います。