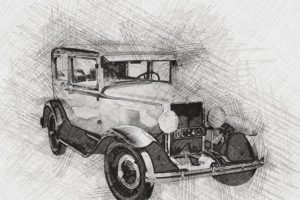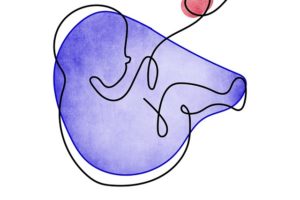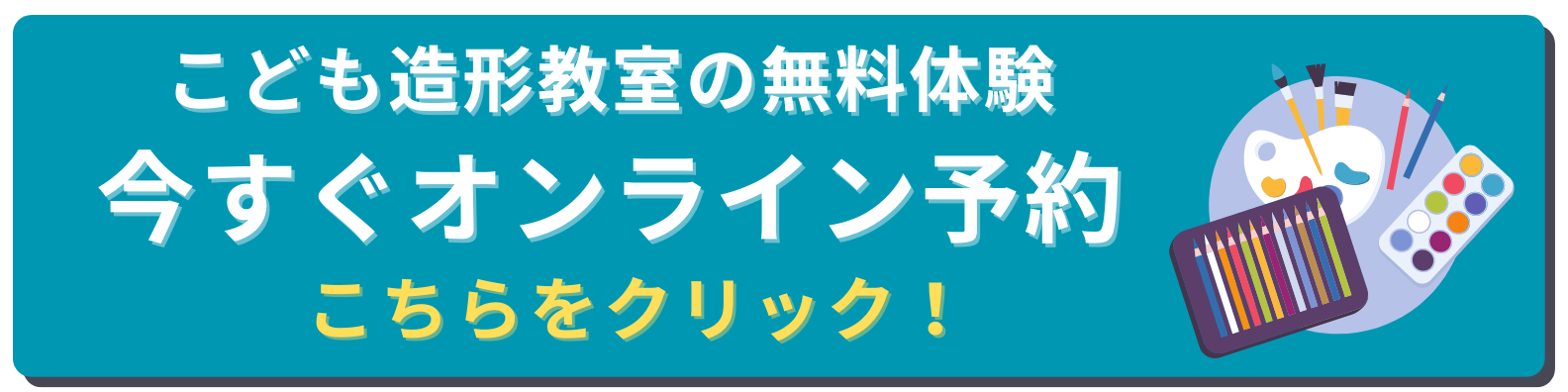こんにちは!母画家道Rinです。
土粘土の焼成【中編1】についてご紹介していこうと思います。
小学校の図画工作、中学高校の美術など、学校で焼き物をするときの材料や用具の準備や指導のポイントを記しました。
参考になれば嬉しいです。
目次
【前編】
1焼成に適した粘土
2焼成するときの工程
3成形のコツ
4粘土の乾燥
5まとめ
【中編1】
1焼成の方法とは?
2まとめ
【中編2】
1釜の種類と選び方のポイント
2まとめ
【後編】
1土粘土のいろいろな表現方法
2まとめ
1焼成(土粘土を焼く)方法とは?
お茶碗や壺、鉢、お皿など、陶芸にあった粘土は、焼くことで水に溶けなくなって、半永久的に保存ができるようになります。
焼成の方法には、一般的な方法として
素焼き
と
本焼き
があります。
焼成方法は、使い道と焼き上がりの色を考えて選択することをオススメします。
小学校の図画工作科で土粘土を使う場合は、素焼きをする場合が多いです。
素焼きとは

焼成温度は、750~900℃くらいで焼いていきます。
テラコッタ粘土の場合は、750℃あたりから、ハニワの色のように変化していきます。
素焼きで焼いたあとに、絵の具で彩色することもできます。
信楽粘土は、焼成すると白っぽくなります。なのでアクリル絵の具で色をつけると発色がきれいにでやすいです。仕上げにニスをぬることも可能です。
本焼きとは

焼成温度は、1250℃以上で焼いていきます。
専門的な知識や専用の窯が必要なので、小学校で取り組むことは中々ありません。
中学校や高校で設備が整っていれば、本焼きまで行うこともあります。また、施設がととのっていなくても、そういった本焼きをしてくれる業者や窯元に頼むこともできます。
釉薬をつけて焼くと水をすわなくなるので、お茶碗やお皿などにも使えるようになります。
楽焼きとは?
楽焼きとは、素焼きをした作品に、800℃前後でも溶ける楽焼き用絵の具や楽焼き用の釉薬をかけて焼く方法です。
発色が鮮やかで、ガラス質のツヤが出て独特の美しい仕上がりになります。
だけど、釉薬の表面に小さなヒビが入ってしまうので、水を入れるような容器には、適していません。
楽焼きに使う粘土は、信楽粘土がオススメです。それは、信楽粘土は焼くと白色になるので、絵の具や釉薬の発色を引き出すのにむいているからです。
2まとめ
今日は、土粘土の焼成とは?【中編1】で、
【中編1】
1焼成の方法とは?
2まとめ
をご紹介しました。
小学校の図画工作、中学高校の美術など、学校で焼き物をするときの材料や用具の準備や指導に役立つとうれしいです。
次回は、
【中編2】
1釜の種類と選び方のポイント
2まとめ
についてご紹介していこうと思います。
などもよかったらご覧ください。
また、質問やアイデア、アドバイスなどあれば、RinARTメンバーズに登録していただけるとメールでRinとやりとりできます。解除も簡単にできます。
お気軽にどうぞ!
最後まで読んでくださりありがとうございました。
母画家道Rinでした。