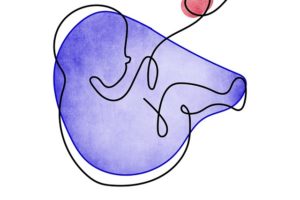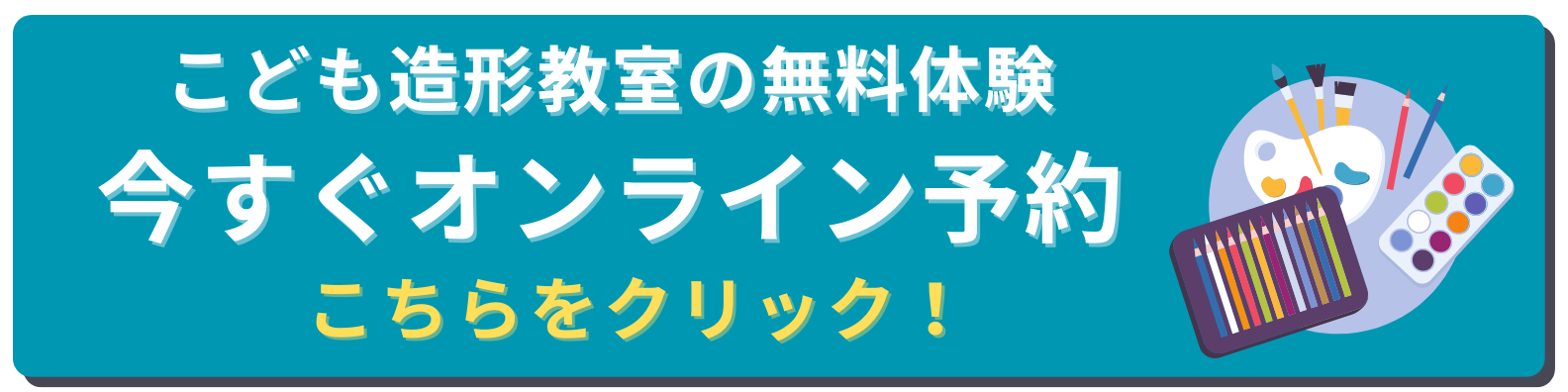こんにちは!母画家道Rinです。
今日は、土粘土の焼成【前編】についてご紹介していこうと思います。
小学校の図画工作、中学高校の美術など、学校で焼き物をするときの材料や用具の準備や指導のポイントなどを記しました。
参考になると嬉しいです!
では、さっそく記事の内容にいきます。
目次
【前編】
1焼成に適した粘土
2焼成するときの工程
3成形のコツ
4粘土の乾燥
5まとめ
【中編1】
1焼成の方法とは?
2まとめ
【中編2】
1釜の種類と選び方のポイント
2まとめ
【後編】
1土粘土のいろいろな表現方法
2まとめ
1焼成に適した粘土とは?小学校の図画工作や中学高校の美術などにおすすめ土粘土
小学校の図画工作や中学高校の美術などで焼き物をすることがあります。
そんなときに、オススメな粘土をご紹介します。
それは
テラコッタ粘土
と
信楽焼粘土
です。
どちらも土粘土のひとつです。
焼いたときの色合いなどが違います。
2焼成するときの工程
小学校の図工や中学高校の美術などで焼き物をするときの焼成の基本的な工程は、
成形
↓
乾燥
↓
素焼き
↓ ↓
楽焼き(800℃前後) 下絵付け・施釉(せゆう)
↓
本焼き(1250℃以上)
3成形のコツ
空気がはいらないように!
空気が入ると焼成するときに割れてしまいます。なので、しっかりと粘土をねんど板にたたきつけるなどして、空気が入らないようにつくります。
厚さは均一に
また、厚みがありすぎると空気が入りやすく、また、焼けムラもおこります。
なので、製作する大きさにもよるけれど、学校でつくるねんど板におけるくらいの大きさならば、厚さが1センチ程で十分です。
粘土の塊をつくる場合は、中をかき出しベラなどで、くり抜くようにします。
接着はどべで
粘土でつくったいろいろなパーツをくっつけたいときは、どべを使います。
土部とは、土粘土を水で溶いたものです。
- つけたいところに、粘土ベラなどで傷をつけ、どべを塗ります。
- つけたいパーツを合わせ、つけたところを指でなじませます。
4粘土の乾燥

焼成するときは、できあがった(成形した)作品を2~3週間かけてしっかりと完成させます。
粘土の厚みがあったり、中まで粘土が詰まっていたりする場合は、さらに時間がかかる場合もあります。
自然乾燥をしていると、表面が乾いているように見えても、中心部は水気が残っていることもあって、乾燥不足になっています。
これを焼成してしまうと作品が爆発してしまって、取り返しがつかなくなってしまいます。
なので、
最初は日陰でじっくり乾かし、白っぽくなってきたら風通しのよい日向で作品を裏返したりしながら乾燥させます。
乾燥中のひび割れには!
乾燥している間に、ひび割れてしまうことがあります。
そんな場合は、作品と同じくらいの硬さの粘土をどべでしっかりと貼り付けて補修することができます。けれど、硬さが違う粘土だと乾燥してくるにつれ剥がれおちてしまうので、粘土の硬さに注意が必要です。
5まとめ
今日は、土粘土の焼成とは?
【前編】
1焼成に適した粘土
2焼成するときの工程
3成形のコツ
4粘土の乾燥
5まとめ
についてご紹介しました。
次回は
【中編1】
1焼成の方法とは?
2まとめ
についてお伝えしていこうと思います。
小学校の図画工作、中学高校の美術など、学校で焼き物をするときの材料や用具の準備や指導のポイントが役だってもらえるとうれしいです。
などもよかったらご覧ください。
また、質問やアイデア、アドバイスなどあれば、RinARTメンバーズに登録していただけるとメールでRinとやりとりできます。解除も簡単にできます。
お気軽にどうぞ!